地域自慢
地域自慢
市毛小学校区には古くから地域にまつわる様々な歴史があります。
今回は「ふるさと市毛」というテーマで皆様にいろいろとご紹介します。
ふるさとを愛し,大切にできる大人を目指します。
市毛という地名の由来
陸前浜街道ぞいに「市」が開かれたという説があります。
桓武平氏の末裔「吉田茂幹」がこの市毛に館を構え,市毛の地名から「市毛六郎」と名乗りました。
桓武平氏の末裔「吉田茂幹」がこの市毛に館を構え,市毛の地名から「市毛六郎」と名乗りました。

早戸川
江戸時代,新田開発のための排水路で,那珂市から那珂川までの約6kmあります。昔は那珂川からサケがのぼることもありました。
大雨で洪水になり「早瀬」になったので「早戸川」と呼ばれるようになりました。

ムナセ堀
堀口の人たちが,早戸川の水をわけてもらおうと灌漑用水して作られました。
しかし作業途中に何らかの理由で中止されてしまい,「むなしい堀」から「ムナセ堀」となりました。
しかし作業途中に何らかの理由で中止されてしまい,「むなしい堀」から「ムナセ堀」となりました。

無二亦寺(むにやくじ)
約340年前,水戸城の馬 の飼育をする場所に,徳川光圀 (水戸黄門)が「そこにお寺を建 てたらいい」と言ったので,無二亦寺ができたそうです。 二度の火事の後,地域の人々 の寄付により現在の場所に再建されました。 徳川綱篠が書いた曼荼羅があります。

稲荷神社
正一位稲荷神社
水戸藩の重臣 肥田和泉の守の氏神
昭和52年に焼失してしまい,平成7年7月に再建されました。
福徳稲荷大明神
鳥居が五つあります。
そのうちの3つには赤いのぼりがついています。
水戸藩の重臣 肥田和泉の守の氏神
昭和52年に焼失してしまい,平成7年7月に再建されました。
福徳稲荷大明神
鳥居が五つあります。
そのうちの3つには赤いのぼりがついています。

鹿島神社 市毛
約430年前にできた神社です。
祭神は武甕槌大神
年に9回のお祭りがあります。
★1月1日歳旦祭
★2月17日祈年祭
★4月3日例大祭
★11月23日秋季大祭
氏子さん達が当番制で守っています。
祭神は武甕槌大神
年に9回のお祭りがあります。
★1月1日歳旦祭
★2月17日祈年祭
★4月3日例大祭
★11月23日秋季大祭
氏子さん達が当番制で守っています。
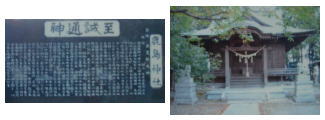
鹿島神社 津田
こちらも約430年前にできた神社で, 戦いの神様をまつっています。
明治25年に再建されました。
戦争に行くときに,お参りしました。
現在も行われているお祭り
★1月1日歳旦祭
★7月14日田植祭
★11月23日秋季大祭
若い男の人達が力石を持ち 上げて力比べしたそうです。
明治25年に再建されました。
戦争に行くときに,お参りしました。
現在も行われているお祭り
★1月1日歳旦祭
★7月14日田植祭
★11月23日秋季大祭
若い男の人達が力石を持ち 上げて力比べしたそうです。
